「提案文が書けない…」その不安の正体は“拒絶への怖さ”
「応募ボタンの前で固まる」のは、誰にでもある感覚
「書かなきゃ」「送らなきゃ」…そう思っているのに、マウスの手が止まる。
その瞬間に湧き上がるのは、「落ちたら恥ずかしい」「何か否定されるかも」という、まだ起きていない“想像上の不安”です。
でもこれは、あなたの中に“挑戦したい気持ち”があるからこそ出てくる感情。
本当にやりたくなければ、そもそも応募のページまで辿り着いていません。
だからこそ、「怖い」と思える自分を、肯定していいんです。
「何もできない自分が提案していいのか…」
その気持ちは自然なこと。でも、それは“できない”証明ではなく、“ちゃんと考えている”証明です。
完璧な文章より、“人柄が伝わる文章”の方が読まれている
多くの人が勘違いしがちなのが、「提案文=実績アピールの場」だという思い込み。
もちろん、実績はあれば強い。でも実績が“ない人”にクライアントが求めているのは、一緒に仕事ができそうか、それだけです。
実際、採用されている人の提案文を見ると、技術よりも“伝わるかどうか”を大切にしている文章が多い。
- 「実績はありませんが、○○について深く知りたいと思っています」
- 「自分の経験が、読者の役に立つかもしれないと思い、応募しました」
そんな一文だけで、「この人、誠実そう」「ちゃんと読者目線を持っていそう」と思われることがある。
つまり、あなたの言葉で“人柄”が伝わる提案文は、スキル以上の力を持つのです。
📝まとめ: 提案文が書けないのは、「スキルが足りないから」ではありません。
それよりも、「断られるのが怖い」「自分がまだ足りていない気がする」——そんな“自分への否定”が怖いだけ。
その壁を超えるには、まずは心の中の声に「分かるよ」と寄り添ってあげること。
そうすれば、提案文は“自己紹介”ではなく、“未来への一歩”になります。
通る提案文の9割は「共感・信頼・誠実」でできている

共感:「あなたの意図をちゃんと読んでいます」という気づかい
提案文を書くとき、多くの人が「うまく書かなきゃ」「すごいと思わせなきゃ」と力が入ります。
でも実は、クライアントが最初に見るのは“文章力”ではなく、“気づかい”です。
たとえば、案件文の中にあった「初心者でもOK。丁寧に読んでくれる人が希望です」という一文。
ここに気づき、
「拝見して、“丁寧に読んでくれる方”という言葉にとても共感しました。私も、読者の悩みにしっかり寄り添う記事が好きで、そういった視点を大切にしています」
と一言添えるだけで、印象はまったく違います。
つまり、“あなたの記事をちゃんと読みました”という姿勢が、信頼のはじまりになるのです。
信頼:経験が浅くても、「読者視点を持てる」ことが武器になる
「実績がないから採用されないかも」──そう思うのは当然です。
でも、実績以上に大切なのは“そのジャンルを読む人の気持ちが分かっているか”です。
たとえば、転職メディアの案件であれば、
「私自身も、30代で転職活動をした際に、キャリアの方向性にすごく悩んだ経験があります。だからこそ、今、転職活動中の方の“迷い”に共感できると思います。」
そんなふうに書けると、それは読者視点を持っている“信頼できる書き手”として見てもらえるのです。
クライアントは、「読者のことを真剣に考えてくれる人」に仕事を任せたいと考えています。
だからこそ、未経験でも“見ようとしている姿勢”を伝えることが大切です。
誠実:「柔軟に対応できます」より、「相談しながら進めたい」の一言が効く
提案文の最後に書く「よろしくお願いいたします」の一文。
実はここにも、誠実さをにじませるチャンスがあります。
「ご希望があれば、柔軟に対応いたします」
という一文よりも、
「最初はすれ違いがあるかもしれませんが、相談しながら、よりよい方向に仕上げていければと思っています」
の方が、一緒に走ってくれる人だという印象を与えます。
これは、「うまくやれます」という“自信”ではなく、「真剣に向き合います」という“誠実さ”です。
クライアントは、完璧を求めているわけではありません。
“一緒に仕事ができそうか”を見ています。
その期待に応えるのは、“背伸びした言葉”より、“丁寧な姿勢”なのです。
このように、共感・信頼・誠実。
この3つさえしっかり伝われば、「実績がない人」でも選ばれる理由になる。
だからこそ、提案文は“売り込み”ではなく、“心を届ける文章”なのです。
【保存版】初心者向け“共感型”提案文テンプレート
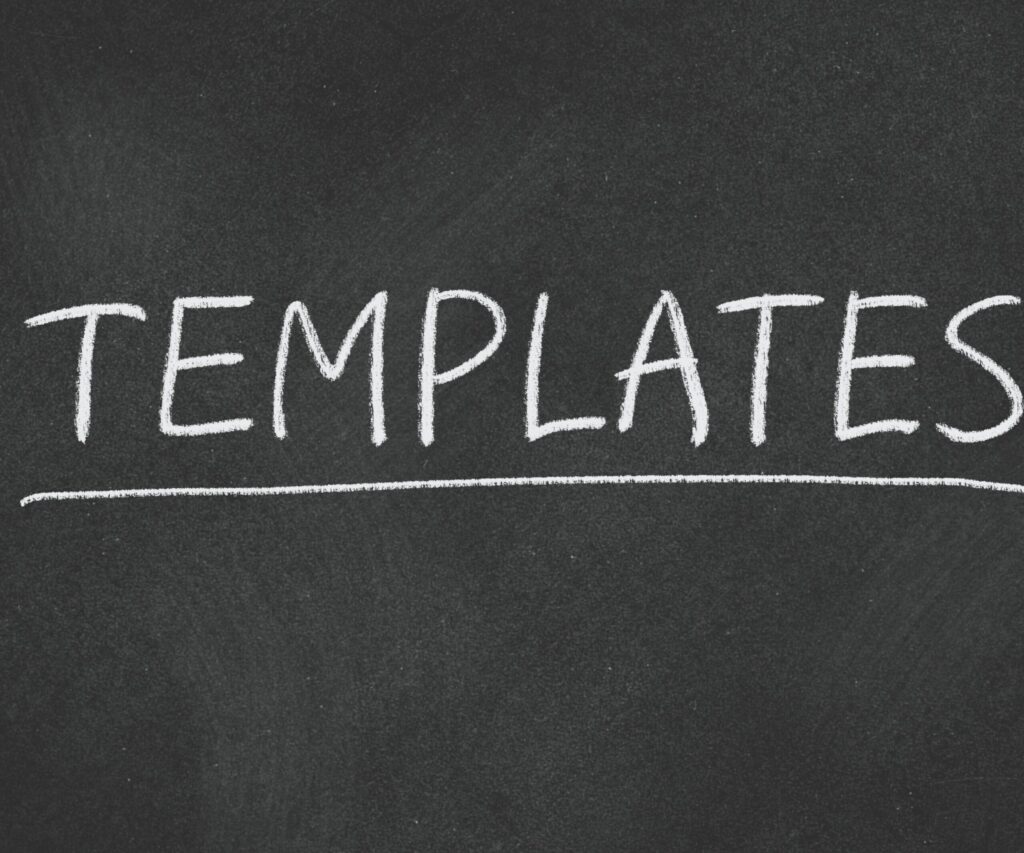
共感→信頼→提案の3ステップで、“気持ちが伝わる文章”になる
「どんな言葉から始めればいいか分からない」
「書いても、読まれずに終わるんじゃないか」
──そう不安になるのは、提案文が“評価される場所”だからです。
でも、実際に選ばれているのは“完璧な文章”ではなく、人柄と誠実さが伝わる提案です。
初心者でも通る提案文には、共通の“型”があります。
🟩テンプレ構造:共感→信頼→提案
【共感】
◯◯というお言葉にとても共感しました。
私も●●な経験があり、そのお悩みやご希望がとてもリアルに感じられました。
【信頼】
私は□□のような経験があり、このジャンルには強い関心があります。
自分の体験をもとに、読者に寄り添う形で記事をお届けできると思っています。
【提案】
ご要望に丁寧に対応させていただきます。
ご相談や修正にも柔軟に対応し、貴社と一緒に“良い記事”をつくれたら嬉しいです。
この型に沿えば、“文章がうまいか”ではなく、「一緒に仕事ができそうか」が伝わります。
つまり、書き慣れていなくても、伝える力は持っていると気づける構造です。
提案文は、あなたの“スタート地点”。
ここで「うまく書けたか」より、「あなたの気持ちが伝わったか」で決まります。
まずはテンプレを使って、“最初の1通”を届けてください。
その一歩が、未来の依頼や信頼に、確実につながっていきます。
まとめ|「採用される人」は、うまい人ではなく“伝える人”

提案文は“スキルアピール”ではなく“対話のきっかけ”
提案文を書くとき、多くの人が「ちゃんと書かないと」「アピールしないと」と身構えてしまいます。でも実は、企業側が本当に知りたいのは“この人と仕事を進めていけるかどうか”。
どれだけ文章が上手でも、どれだけ経歴が立派でも、そこに「一緒に進めたい」と思える気配がなければ採用にはつながりません。
「〇〇のジャンルは得意です」「こんな実績があります」よりも、 「〇〇という読者の悩みに共感しながら、一緒に反応が取れる記事を考えたいです」というひとことが心に届く。
提案文は“完璧な履歴書”ではなく、“これから一緒に仕事をしていけるか”を見極めるための“対話の入り口”なのです。
たった1通でも、“誠実な対話”になっていれば、「この人にお願いしたい」が生まれます。
「まだ何も書いてない自分」こそ、伸びしろしかない
「実績がない」「経験がない」「文章に自信がない」——そう思って、ずっと手が止まっていませんか?
でも、企業の採用担当者が本当に見ているのは、「今何ができるか」だけではありません。 「この人は、ここからどう伸びていくか」 「一緒に成長していけるか」——そんな“これから”の可能性です。
だからこそ、実績がゼロでも「相手を理解しようとする姿勢」や、「自分なりの考えで言葉を組み立てようとする視点」が、最大の魅力になります。
何も書いてない自分を責めなくて大丈夫です。 今から、1通の提案を書けばいい。 今から、1記事のポートフォリオを作ればいい。
その一歩を踏み出した人にだけ、ライターとしての未来は拓けます。
あなたの言葉を、待っている企業は必ずいます。

